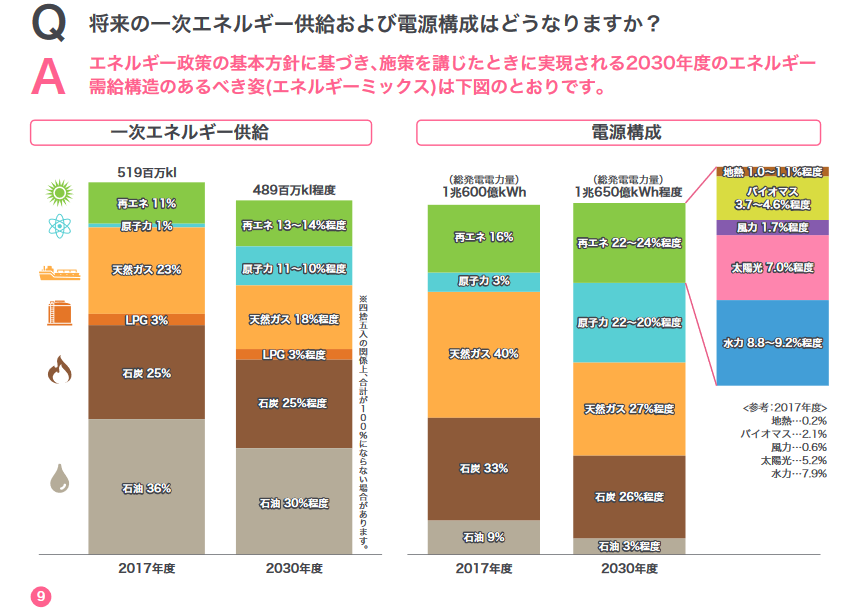菅首相は所信表明演説で「2050年、温室効果ガスゼロの脱炭素社会を目指す」と宣言しました。
政策関連銘柄のテーマとして「再生可能エネルギー」が注目されています。
このブログでは私なりにテーマ研究をしています。
シリーズ第3回「再生可能エネルギーの事業環境」、第3回はエクソンモービルは再生可能エネルギーをどう評価しているかを見てみます。
エクソンモービル(XOM)は世界最大の石油メジャー企業です。米国の政府とも一定の距離を置き、発展途上国での原油採掘ビジネスを独力で切り開くとんでもない企業です。
XOMは世界のトップレベルの大学出身で、理系分野の博士や国際情勢を分析するアナリストを社員として雇用しています。
ときには米国のCIAとも対等にわたりあえるほどのインテリジェンスを有する同社は、自社の事業を中・長期的に駆逐するかもしれない再生可能エネルギーについて綿密な研究を日々重ねています。
そんなXOMは、再生可能エネルギーをどう評しているか?
XOMの全貌を描いた大著「石油の帝国」(ダイヤモンド社)から引用します。
『2007年までには、本社のプランナーは、太陽光・風力技術の状況については確かな理解を得たと感じていた。政府の補助金を得たこれらの産業の急速な成長を予想していたものの、エクソンモービルは太陽光も風力も本格的な脅威とはみなしていなかった。一つには、太陽光・風力はいずれも電力供給のシステムであり、石油産業の心臓部とも言うべき輸送燃料に対してはほとんど影響がなかったからである。エクソンモービルが発電のために供給するガスは、当面の間は太陽光や風力に対して十分な価格競争力があった。』(P441)
いかがでしょうか。
同書は2012年の刊行で、情報としては少し以前の時系列に入ります。
それでも、この10年間で太陽光・風力発電には(私が知る限り)革命的なブレークスルーは起きていません。
引用したくだりは、現在の太陽光・風力発電の事業環境にもだいたい“本線を突いている”と思います。
再生可能エネルギーとしての太陽光・風力発電には、大きなビジネスの可能性がある。それでも、エネルギーのポテンシャルとしては、石油産業にはまだしばらくは脅威にすらならない。
再生可能エネルギーの可能性には限界がはっきりと見えている。
XOMが導いたこの結論を、私も再生可能エネルギーの全体像として頭に入れておきます。
【参考】
「石油の帝国」はエクソンモービルの全貌を描いた大著です。著者のスティーブ・コール氏はピュリッツァー賞を受賞した記者で、その膨大な取材量と資料としての正確性に同書のクオリティーは担保されています。
上下2段組で600ページ超というスーパーヘビー級の一冊ですが、エクソンモービルを通じて石油メジャーやエネルギー産業のことを学ぶには格好のテキストです。